年金に関する深い考察、大変興味深く拝見いたしました。ご自身の年金額をシミュレーションされ、その結果(年額134万円)について「多いのか少ないのか」と考えるのは、非常に現実的な一歩です。この考察をさらに専門的で読み応えのある記事にするため、年金の仕組みと老後資金形成について、より詳細な視点から掘り下げてみましょう。
自身の年金額を知るということ:公的年金の構造と受給額のリアル
ご提示の年額134万円という数字は、単なる金額以上に、日本の公的年金制度の構造を理解するための重要な手がかりとなります。

公的年金の「二階建て」構造の再確認
会社員の方が受給する年金は、「老齢基礎年金(1階部分)」と「老齢厚生年金(2階部分)」の二階建て構造になっています。
- 20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)すべて納付した場合に満額が支給されます(令和6年度は年額816,000円)。
- この部分は、原則として全員一律です。
- 現役時代の報酬と加入期間によって大きく差が出る部分です。
- 年額134万円の内訳から、この厚生年金部分が「多いか少ないか」を判断することになります。
ポイント: 年額134万円から基礎年金満額(約81.6万円)を差し引くと、残りが厚生年金の見込み額となり、これが現役時代の報酬を反映した部分です。
—
厚生年金決定のメカニズム:標準報酬月額の決定と落とし穴
「老齢厚生年金は標準報酬月額で決まる」という認識は正確です。しかし、その「標準報酬月額」の決定メカニズムには、給与体系に潜む「年金の落とし穴」があります。

標準報酬月額の定義と報酬の範囲
標準報酬月額とは、毎月の給与を一定の幅(等級)に区分けしたものですが、ここでいう「給与」の範囲が極めて重要です。
- 基本給はもちろん、残業代、役職手当、住宅手当、家族手当、通勤手当など、労働の対償として経常的に受けるもののすべてが含まれます。
ご指摘の誤解を深掘り!
「基本給のみで判断し、手当が除外される」という認識は、社会保険料算定の観点からは誤りです。支給総額が同じであれば、原則として標準報酬月額は同じになります。
知っておくべき「固定的賃金」と「非固定的賃金」
年金の算定基準となる標準報酬月額は、毎年4月・5月・6月の報酬を基に決定されます(定時決定)。この決定額には、基本給、固定的な手当だけでなく、変動する残業代もすべて含まれます。
この仕組みから、残業が多かった時期の標準報酬月額が高いと、その後の1年間、より多くの保険料を納めることになり、将来の年金額増加に繋がります。
—
老後資金を増やすための具体的な戦略的取り組み方
年金シミュレーションの結果を踏まえ、「もっと欲しい」という目標を達成するためには、年金制度の特性を理解した戦略的な老後資金形成が不可欠です。
1. 資産形成の「三本柱」の最適化
公的年金を補完する老後資金は、以下の三本柱で構築するのが現代のセオリーです。
- 公的年金(1階・2階): 制度を最大限活用する。
- 私的年金(3階):
- iDeCo(個人型確定拠出年金)の積極的な活用。掛け金が全額所得控除になり、税制優遇を受けながら年金を積み増せます。
- 自助努力(資産運用): 新NISAなどの非課税制度を活用し、インフレに打ち勝つための強力な資産運用を行う。
2. 「働き方」の戦略的選択
在職老齢年金制度の理解
60歳以降も厚生年金に加入して働く場合、給与と年金の合計額が高すぎると、年金の一部または全額が支給停止されることがあります。この制度を理解し、年金をもらいながら働く際の最適な給与水準を事前にシミュレーションすることが重要です。
繰り下げ受給の検討
本来の受給開始年齢(原則65歳)から最大75歳まで受給開始を遅らせる(繰り下げる)ことで、年金額を最大84%増やすことができます。健康状態や他の資産とのバランスを考慮し、最も有効な戦略を選択しましょう。
まとめ:年金制度は「知っている人」が得をする
制度の正確な理解と、iDeCoや新NISAを組み合わせた戦略的な資産運用こそが、老後資金の不安を解消する鍵となります。まずは、ご自身の年金記録を「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確認することから始めましょう!
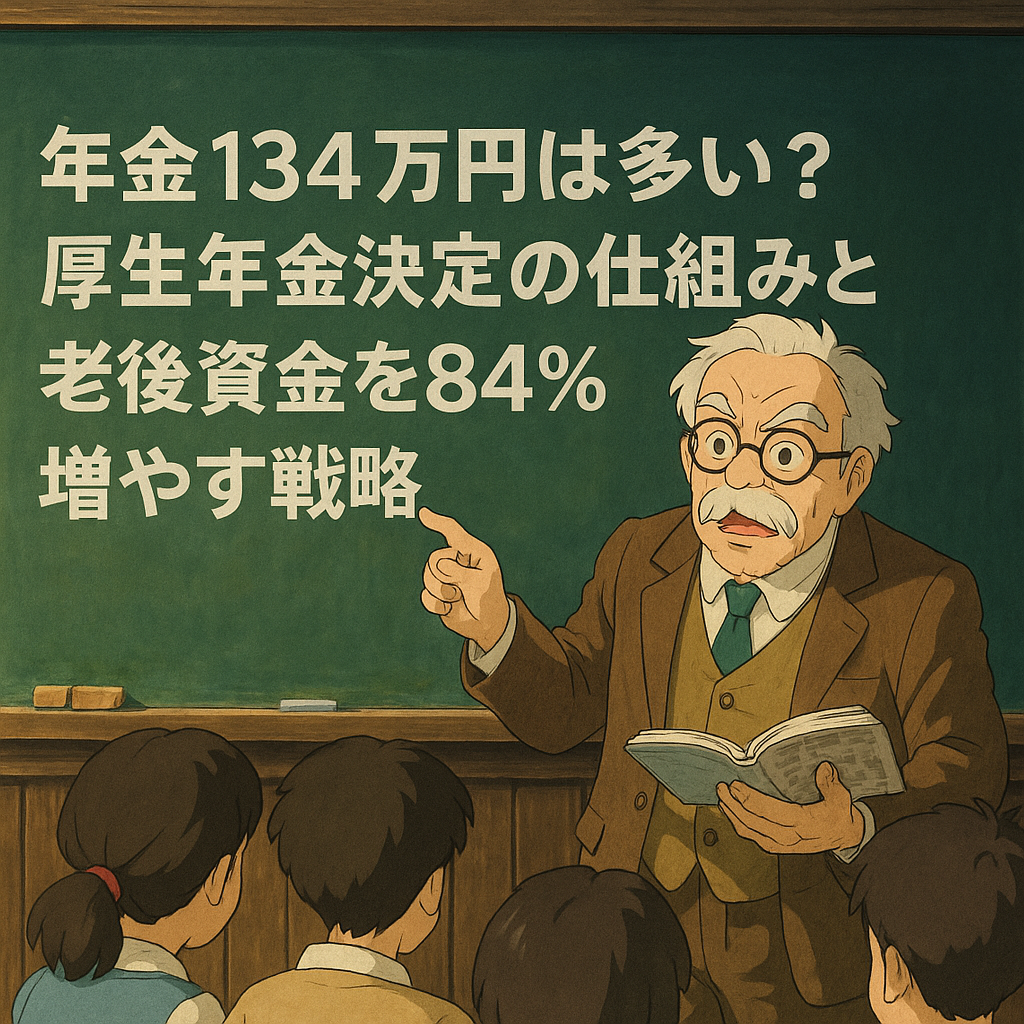

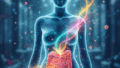

コメント