定年年齢を70歳にする企業が少しずつ現れています。一方で「70歳まで働くのは不安…」という声も。そこで本記事では、70歳まで働くことの金銭面のメリットを、制度・数字・実務の観点からわかりやすく解説します。
🔖 この記事の結論(3行)
- 長く安定収入:70歳まで継続雇用なら給与収入が伸び、老後資金の積み増しに直結。
- 年金面が有利:厚生年金は原則70歳まで加入可。繰下げ受給で最大+42%(70歳開始)。
- 資産形成を継続:NISA・iDeCo等を活用して、リスクを抑えつつ運用期間を伸ばせる。
70歳定年制の会社はどれくらいある?
令和3年4月施行の高年齢者雇用安定法により、企業には「70歳まで就業機会を確保する」ための努力義務が課されました。具体策は、①定年廃止、②定年の70歳への引き上げ、③70歳までの継続雇用制度など。

📊 令和6年「高年齢者雇用状況等報告」では、70歳までの就業確保措置あり:31.9%(約3社に1社)。うち「定年の引き上げ」方式は2.4%と少数で、70歳定年そのものの導入はまだ限定的です。
70歳まで働く金銭メリット
| 観点 | 65歳定年 | 70歳定年 | メリットの要点 |
|---|---|---|---|
| 収入 | 65歳以降は年金中心/再就職で減収が一般的 | 現職の給与を+5年維持できる可能性 | 可処分所得の確保で取り崩しを遅らせる |
| 老後資金 | 積立余力が限定的 | 積立期間+5年で貯蓄・投資を上乗せ | リスク許容度を保ちやすい |
| 退職金課税 | 勤続年数に応じた退職所得控除 | 勤続延長で控除枠が拡大 | 手取り退職金の増加が見込める |
| 公的年金 | 65歳から受給が原則 | 厚生年金に70歳まで加入可/繰下げで最大+42% | 生涯受給額の底上げ |
| 資産形成 | 60代の元本割れが心理的負担 | 給与収入でNISA・iDeCo等を継続 | 長期分散・時間分散を維持 |
資産形成を有利にする:NISA/iDeCoの活用

- 給与収入が続くあいだは、毎月の積立額をキープしやすい(取り崩し回避)。
- 40代・50代スタートでも、70歳までの延長で“運用×積立”の両輪を回せる。
- NISAは年齢上限なし。iDeCoは制度上の加入年齢要件があるため、ご自身の加入可否・拠出上限は必ず最新要件を確認。
💡運用ヒント:70歳までは「積立:インデックス中心」「一括:分割購入」で時間分散。現金クッション(生活費12〜24か月)も確保して、相場変動時も積立を止めない設計に。
厚生年金の増額と「繰下げ受給」
厚生年金は原則70歳まで加入可能。65歳以降も働いて保険料を納めると、将来の年金が増えます。また、受け取り開始を遅らせる繰下げ受給は、1か月あたり+0.7%の増額。70歳開始なら+42%の年金になります。
⏱️ 受給設計の例
- 65〜69歳:給与収入で生活。年金は繰下げて増額を狙う。
- 70歳:退職+年金受給開始(増額後)。取り崩し開始を遅らせ、寿命リスク(長生きリスク)に強い家計へ。
勤続延長で「退職所得控除」が拡大
勤続年数が増えると退職所得控除(課税対象を小さくする枠)も広がるため、同額の退職金でも手取りが増える可能性があります。会社規程(退職金制度)と合わせて確認しましょう。
⚠️ ご注意:税・社会保険・各制度の要件は改正されることがあります。会社の就業規則/退職金規程・年金加入状況・最新の公的情報をセットで確認してください。
「70歳定年が不安」への実務チェックリスト
- 健康面:年1回の人間ドック/運動・睡眠ルーティンを確保
- 働き方:職務の棚卸し・負荷の調整(時短/配置転換の相談窓口)
- お金:生活費・保険・ローンの見直し、取り崩しゼロ期間の試算
- 制度:継続雇用条件・賃金水準・評価基準の確認
- 投資:NISA/iDeCoの積立比率・現金クッションの再設定
まとめ:70歳定年制は「老後の安心資金」を作るチャンス
勤務先の定年が70歳になると、収入の維持・年金増額・資産形成の継続という3つの追い風が同時に得られます。ライフプランの手直しは必要ですが、金銭的には前向きな変化になり得ます。
よくある質問(FAQ)
Q. 70歳まで働けば誰でも年金は+42%になりますか?
Q. iDeCoは70歳まで掛けられますか?
Q. 継続雇用と「70歳定年」は同じですか?
関連記事
![]()
- 退職金が消えた…老後資金の資産運用失敗談3選と学ぶべき教訓(2025年8月30日)
- 年収400万円で独身が生活する家計の目安|手取り・支出・貯蓄の黄金比率(2025年8月27日)
- 「日本の富裕層は何世帯?純金融資産1億円以上の実態と増加する5つの理由」(2025年8月21日)
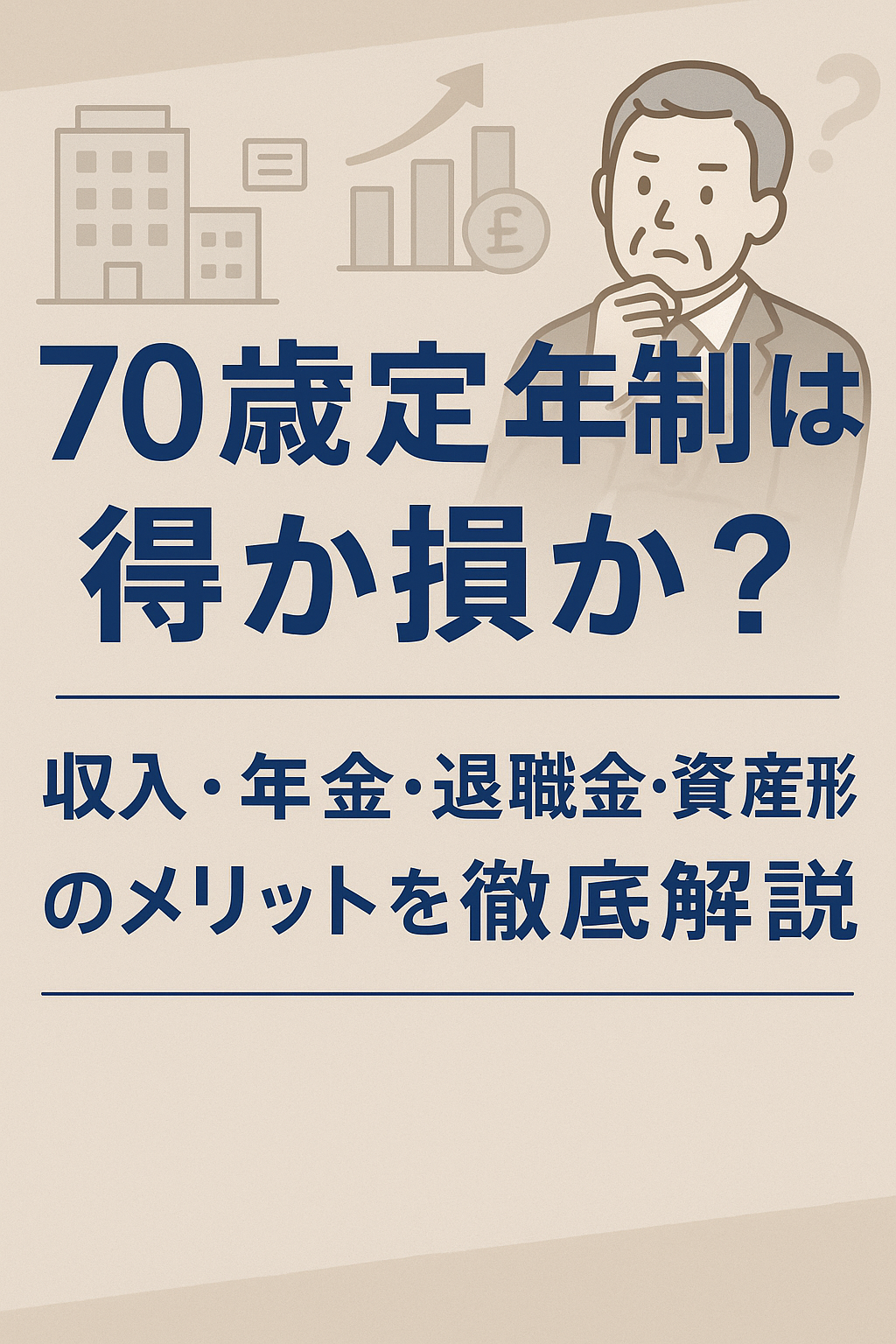
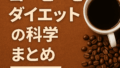


コメント