唐突で申し訳ないのですが、身内に不幸があると悲しいですよね。そして残された方には生活があります。生活するための収入が減ってしまう可能性があるわけです。そのために今回のテーマである「遺族年金」というものを紹介させていただきたいと思います。
通常、年金というと皆さんご存知の通り、自身が65歳になったら支給される(繰上げ、繰下げはなしとして)かと思います。そちらは有名ですが、意外と遺族年金を知らないかたは多いと思います。こちらは申請しなくては支給されない制度ですので、是非基本的な部分を押さえていただければと思います。
遺族年金は、日本の公的年金制度の一部で、家族を支える主な収入源となる人(被保険者や受給者)が亡くなった場合に、その遺族の生活を支援するために支給される年金です。遺族年金には主に「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。それぞれの仕組みを以下に詳しく説明します。

1. 遺族基礎年金
遺族基礎年金は、主に国民年金に加入している人が亡くなった場合に、その遺族(子どもがいる配偶者または子ども)に支給されます。
支給対象者
- 被保険者が死亡したとき、その配偶者(子どもがいる場合)または子ども自身が対象です。
- 子どもとは、以下の条件を満たす人を指します:
- 18歳到達年度末(高校卒業年齢)までの子
- 障害等級1級または2級に該当する20歳未満の子
支給条件
以下のいずれかに該当する場合に支給されます:
- 国民年金加入者が死亡した場合
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている人が死亡した場合
また、亡くなった被保険者が保険料を十分に納付していること(直近の1年以内に未納がないなど)が条件となります。
支給額
- 基本額(令和5年度時点):
- 779,300円/年 + 子どもの加算額
- 子どもの加算額:第1子・第2子は各223,800円、第3子以降は各74,600円
- 例:子どもが2人いる場合 → 779,300円 + 223,800円 + 223,800円
2. 遺族厚生年金
遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた人が亡くなった場合に、その遺族に支給されます。
支給対象者
以下の遺族が対象になります(受給順位が高い方から):
- 配偶者(事実婚を含む)
- 子ども(遺族基礎年金と同じ条件)
- 父母
- 孫
- 祖父母
支給条件
- 亡くなった人が厚生年金の被保険者であった、または受給資格を満たしている場合
- 亡くなった人が老齢厚生年金を受け取る資格があった場合も支給対象となる
支給額
- 亡くなった被保険者の報酬比例部分(老齢厚生年金の2/3相当額)が支給されます。
- 子どもがいる場合は遺族基礎年金と併せて受給可能です。
注意事項
- 働いていた方が若いときに亡くなった場合でも、報酬比例部分は加入期間の短さに基づいて計算されます。
- また、配偶者が40歳から65歳未満の場合、さらに「中高齢寡婦加算」が支給されることがあります。
3. 併給調整について
遺族基礎年金と遺族厚生年金を同時に受け取ることができる場合がありますが、他の年金(例:自分自身の老齢年金など)と重複する場合、全額を受け取れないことがあります。このような場合は調整が行われます。
4. 申請方法
遺族年金は自動的に支給されるものではなく、申請が必要です。申請の際には以下の書類が必要となります:
- 被保険者の死亡を証明する書類(死亡診断書など)
- 住民票や戸籍謄本
- 被保険者の年金手帳や基礎年金番号が分かる書類
- 銀行口座情報
申請先は、市区町村役場や年金事務所です。
遺族年金は、亡くなった方の年齢や加入状況、家族構成によって金額や受給対象者が異なりますので、正確な情報を得るために年金事務所に相談することをおすすめします。
遺族年金は、一定の条件を満たす場合に支給されますが、条件を満たさない場合や特定の事情がある場合には支給されないケースがあります。以下に、遺族基礎年金や遺族厚生年金が支給されない主なケースを説明します。
遺族基礎年金が支給されないケース
- 被保険者の保険料未納がある場合
- 被保険者が亡くなる直前に、保険料の未納期間が多い場合(具体的には、死亡日までの1年間に保険料の未納がある場合)、遺族基礎年金は支給されません。
- また、過去の納付状況が「納付済み期間(免除期間を含む)」が原則として「加入期間の3分の2以上」でないと支給されません。
- 子どもがいない配偶者の場合
- 遺族基礎年金は、子どもがいない配偶者には支給されません。遺族基礎年金の対象となるのは、「子どもがいる配偶者」または「子ども本人」のみです。
- 子どもが支給対象外となる場合
- 子どもが18歳到達年度末を過ぎた場合(高校卒業相当の年齢)や、20歳を過ぎた障害等級1級または2級に該当しない場合には、遺族基礎年金は支給されません。

遺族厚生年金が支給されないケース
- 遺族基礎年金と同様に、保険料未納がある場合
- 厚生年金の被保険者が亡くなった場合、同様に保険料未納が一定以上あると支給されません。
- 受給資格者がいない場合
- 遺族厚生年金は、配偶者、子ども、父母、孫、祖父母のいずれかがいなければ支給されません。
- さらに、これらの遺族が年齢や条件を満たさない場合も支給対象外となります。
- 例:配偶者が亡くなった厚生年金被保険者の遺族であっても、扶養されていない配偶者(離婚している元配偶者など)は対象外です。
- 受給資格が他の制度により制限される場合
- 例えば、配偶者が再婚した場合、遺族厚生年金の受給資格を失います。
- 年金の併給調整による制限
- たとえば、自分がすでに老齢年金を受給している場合、遺族厚生年金と併給はできません。ただし、一部または高い金額の年金を選択する「選択受給」の形となります。
遺族年金全体で支給されない主なケース
1. 死亡が業務上の原因でない場合(例外あり)
- 業務上の死亡事故(労働災害)が原因で亡くなった場合、労災保険からの給付(遺族補償年金)が優先され、遺族年金は支給されない場合があります。ただし、業務外の原因で亡くなった場合は遺族年金が支給される可能性があります。
2. 遺族が一定の収入を得ている場合
- 遺族自身が一定以上の収入を得ている場合、遺族年金の対象外となることがあります。
- 例えば、一定以上の給与収入や老齢年金を受け取っている場合には、併給調整が行われ、結果的に遺族年金が支給されないことがあります。
3. 偽りの申請があった場合
- 虚偽の申請があった場合(例えば、死亡した人が実は生存していた、など)、遺族年金の受給資格を失うことがあります。
よくある質問:遺族年金が支給されない理由が不明な場合
- 万が一、遺族年金の申請が認められない場合は、理由が説明されますが、納得できない場合は再審査請求が可能です。疑問がある場合は、日本年金機構や市区町村役場に相談し、具体的な理由を確認してください。
参考情報
- 日本年金機構の公式サイトでは、遺族年金について詳細に説明されています: 日本年金機構公式サイト
- 遺族年金の申請や相談は、お近くの年金事務所で行えます。

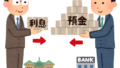


コメント