こんにちは。
このブログでは、働く人の「これから」を応援するために、退職や転職、そして雇用保険の制度について分かりやすくお伝えしています。
■ 話題になっている「退職代行モームリ」と“非弁行為”の問題とは?
最近ニュースなどで、「退職代行モームリ」に警察の捜査が入ったという報道をご覧になった方も多いのではないでしょうか。
この事件の背景には、「弁護士資格を持たない人が法律的な交渉を代行する」という“非弁行為”の疑いがあるとされています。
退職代行サービスは、会社を辞めたいけれど直接伝えるのがつらい人たちを助ける存在として、ここ数年で急速に広まりました。
しかし、退職の場面では「未払い賃金」や「有給の扱い」など、法律的な判断が絡むことも多く、そこに弁護士以外が関わると法に触れてしまう可能性があるのです。
もちろん、退職代行自体が悪いわけではありません。
中には弁護士が監修している安心なサービスもあります。
ただ、「どこまでを代行してもらえるのか」「法律の範囲内かどうか」を確認しておくことが、利用者自身を守ることにつながります。

■ 退職するときに知っておきたい大切なこと
1. 「自己都合」と「会社都合」では、退職後の扱いが大きく違います
退職には大きく分けて二つのタイプがあります。
ひとつは、自分の意志で辞める「自己都合退職」。
もうひとつは、会社の都合(倒産や解雇など)による「会社都合退職」です。
この違いは、ハローワークで受けられる「失業給付(雇用保険)」の開始時期や支給期間に大きく影響します。
会社都合の場合は、待機期間が短く、給付日数も多くなる傾向があります。
もし納得できない理由で「自己都合」と処理されてしまった場合は、労働基準監督署やハローワークに相談してみましょう。
2. 雇用保険(失業給付)の基本を押さえよう
退職後にすぐ次の仕事が決まらない場合、雇用保険から「基本手当」を受け取ることができます。
これは、再就職までの生活を支えるためのとても大切な制度です。
主なポイントは次の通りです:
- 受給資格:退職前2年間に12か月以上、雇用保険に加入していること
- 給付額の目安:退職前6か月の給与の平均(賃金日額)の約5〜8割
- 手続きの流れ:離職票を受け取り、ハローワークで求職申込み → 7日間の待機 → 支給開始
自己都合退職の場合、以前は「3か月の給付制限」がありましたが、2025年4月からは2か月→1か月に短縮されています。
これは、再就職を目指す人にとって嬉しい改正ですね。
3. 教育訓練給付制度もチェック
最近は「学び直し」や「スキルアップ」を支援する制度も充実しています。
例えば、専門学校や資格取得の講座を受けるときに、費用の一部を国が支援してくれる「教育訓練給付金」という制度があります。
退職後に新しいキャリアを考える方には、ぜひ検討してほしい制度です。
![]()
4. 退職金・給付金を忘れずに確認
退職前に「退職金制度があるか」「いつ支払われるのか」を確認することも大切です。
会社によっては、勤続年数が短くても一定の退職金を受け取れるケースもあります。
また、退職金と雇用保険の給付は同時に受け取ることも可能です。
■ 退職前にやっておきたいチェックリスト
- 退職理由は明確?(自己都合か会社都合か)
- 雇用保険の加入期間を確認
- 離職票を必ずもらう
- 貯金や給付金で生活設計を立てる
- 退職代行を使う場合は、法的に安全なサービスを選ぶ

■ 最後に:焦らず、自分を守る選択を
退職は、新しい人生のスタートでもあります。
「辞めること」は悪いことではありません。
でも、制度を知らないまま辞めてしまうと、受け取れるはずの支援を逃してしまうこともあります。
ニュースで話題の「退職代行モームリ」の件は、私たちに“退職の正しい知識を持つことの大切さ”を教えてくれたように思います。
焦らず、法律の枠内で、自分を守る選択をしていきましょう。
あなたの次の一歩が、前向きで安心できるものになりますように。

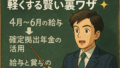
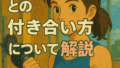

コメント