「砂糖の効果」は「甘味」をつけるだけではない
砂糖は調味料の中でも代表格の一つであるくらいメジャーな調味料です。皆さん絶対と言っていいほど使ったことあると思います。
私もコーヒーに入れたり、料理で使用することがあります。主に甘味を付ける目的ですね。しかし砂糖には他の役割があることをご存知でしょうか?
料理が得意な方はご存知かもしれませんね。
砂糖は食品加工や調理に使う際、「甘味」をつけるだけではなく、非常にたくさんの役割があるのです。これを専門用語で「物性」といいます。
まずは「砂糖の物性」について、次にまとめてみます。
菓子類に利用した場合の「砂糖の物性」の主なものをまとめると、以下の7つになります。
「甘味以外」にも、いろいろな「効果」がある
【1】甘味
・適量を使用することで、ほかの調味料の味と調和させる。それぞれの味を際立たせる効果もある。
【2】親水性
・乳成分、カカオ成分の味を安定させる
・食品の保水性、しっとり感を保つ。乾燥を防止する
・でんぷんの老化(パサパサ感)を遅らせる

例)スポンジケーキ、カステラ、和菓子
【3】安定性
・食品中の水分を結合水に変え、酸化を遅らせることで、油脂成分の風味を安定させる

例)ビスケット、クッキー、チョコレート
【4】造形性
・パン、カステラなどのふっくらした状態を保つ

【5】着色と香味
・メイラード(糖とアミノ酸)反応により、おいしそうな色(茶色)、いい香りをつける
例)パン、クッキー
【6】たんぱく質の安定
・カスタードプリンなど、たんぱく質の凝固温度を高め、口当たりをよくする

【7】冷凍変性防止
・冷凍による劣化を防ぐ

例)クリーム、スポンジ類、冷凍すり身など
砂糖には甘味をつける以外にも、こんなにたくさんの効果があるのです。
そして、この「砂糖の物性」を上手に利用しているのが、じつは「和食」です。
和食は「砂糖の物性」を上手に利用している
砂糖を使うことで、食品をしっとりさせて口当たりをよくしたり、日持ちをさせたりする「伝統的な知恵」が和食にはあります。
たとえば、コンニャクを普通にだしとしょうゆで煮てもなかなか味がしみ込みません。そこに下茹でのときに大さじ1杯の砂糖を入れると、味がしっかりしみ込みます。

また生魚の下ごしらえに熱いお湯をかけて臭みをとる「霜降り」という技術がありますが、これも少量の砂糖を溶かしたお湯を使うと、形が保たれ、臭みがとれるのです。
また、お菓子の製造においても「砂糖の物性」の利用は必須です。
まず卵白を泡立ててホイップ状にするメレンゲは砂糖なしではしっかり泡立ちません。生クリームも砂糖を使って泡立たせることで口当たりがよくなります。
それからチョコレートはカカオバターを安定させて口溶けをよくするために砂糖が必要です。砂糖以外の甘味料、たとえば果糖をチョコレートに使っても、砂糖の「あの口溶け」は出ないのです。

こうした「砂糖の物性」を無視して「たんなる甘味」としてとらえてしまうから話がおかしくなるのです。
当然ですが、「人工甘味料」「天然甘味料」には、こうした「砂糖の物性」はありません。
砂糖はカロリーが高いから低カロリー甘味料を使えばいいという「たんなる置き換え」では、砂糖が醸し出す「総合的なおいしさ・口当たりのよさ」が生まれません。
それを補うために添加物が使われることにもなります。さらに、そこに前回、前々回の記事で述べた「低糖質甘味料の味のクセ」ものってくるわけです。
たとえば、プリンは牛乳、卵、砂糖というシンプルな材料で作られるお菓子です。この場合、砂糖は「しっとり感」「ねっとり感」を出すという仕事をします。
でも、砂糖をカットしてしまうと、それが出ないから、「ゼラチン」「寒天」あるいは「増粘多糖類」を使うことになるわけです。
「砂糖の物性」をほかの添加物で置き換えようとするのは無理がある話なのです。とりわけチョコとプリンは砂糖を使わず、他のものに置き換えるのは難しいと思います。
「糖質オフスイーツがおいしくない」のは理由がある
それから今回は触れませんが、でんぷんにも「でんぷんの物性」があります。たとえば「口当たりよく固める」「弾力を与える」「形よく成形する」などです。
これも同じで、「でんぷんの物性」を無視して大豆粉などで「単純な置き換え」をすると、口当たりが悪くなったり、いい形にならなかったりします。それもやっぱり添加物を使って固めたり、形を保ったりすることになります。
いずれにしても、「置き換え」で作られた「糖質オフスイーツ」は、加工の工程を考えるだけでも、おいしいものを作るのが非常に難しいことがおわかりいただけると思います。
もちろん、メーカーもがんばってはいるのです。しかし、いまのところは「砂糖の味や物性」を代替できる技術がないのです。
実際に今回、糖質オフスイーツを編集スタッフにも試食してもらいましたが、「おいしくない」「バサバサで口当たりが悪い」「後味が悪く、舌にいつまでも残る」などすこぶる評判がよろしくありませんでした。
ここ最近の「糖質オフダイエット」の影響で、みんなが砂糖・でんぷんを嫌うようになりました。
しかし、砂糖は本当に「悪者」なのでしょうか?
砂糖ほど重要な調味料はない
私は「砂糖ほど重要な調味料はない」と思っています。
「余人をもって代えがたい」という言葉がありますが、砂糖は「ほかのものでは代えられない力」を持った「魔法の調味料」なのです。
料理に甘味をつける調味料に「みりん」があります。料理に砂糖を使うことを「邪道」という言い方をする人がいます。砂糖を使わず、「みりん」のみで十分だというのです。
しかし砂糖の主成分は「ショ糖」、みりんの主成分は「ブドウ糖」です。
砂糖とみりんはそれぞれの性質をもち、料理によって向き不向きもあるから単なる甘味の置き換えでは済みません。
要は「使い分け」が大事なのです。料理をする人なら肌感覚でわかると思いますが、みりんは砂糖の代わりにはなりません。同じく砂糖もみりんの代わりにはなりません。「甘味をつけるならなんでもいい」という話ではないのです。
ちなみに「みりんの独特の匂い」を解消すべく開発したのが「みりん酒」です。上品な甘さと、日本酒の酸味で、あたかも料理屋さんみたいな味になります。少し面倒ですが、ぜひ作って試してみてください。
|
|
もちろん砂糖にもデメリットはあります。「結晶化しやすい」「微生物が利用しやすい」「虫歯になりやすい」などです。
また甘味が単調、使いすぎると甘すぎる、糖質が高いといったことです。しかし、これは適量を使えばいいだけの話です。
9割の人が知らない「砂糖の使い方」
『食品の裏側』では「調味料の裏側」についても詳しく解説しましたが、要は、砂糖は「使い方次第」なのです。
砂糖そのものが悪いのではなく、「使いすぎ」が問題なのです。
上手に適量を使うことで、調理においては「砂糖の物性」を生かしておいしく仕上げることができるし、食べる際においても、やっぱり「砂糖の純粋な甘味」は最強だと思います。

私は料理をする際に、砂糖の甘味効果は半分、あとはその他の物性の効果が半分という気持ちで使っています。
『安部おやつ』では砂糖の物性を生かした使い方をしていますが、どのおやつも決して甘ったるすぎることなく、低脂質でとてもヘルシーです。
お菓子は砂糖を使って伝統的な製造法で作られたものがやっぱりおいしいです。
スイーツは「嗜好品」であり「心の栄養」です。本当においしいと思えるものを少量食べるのがいいのではないかと私は思います。
砂糖を一方的に「悪いもの」と決めつけるのではなく、よさを見直して、上手に取り入れてほしいと私は心から願っています。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/47d3b40f.2427fe02.47d3b410.9d842b64/?me_id=1413751&item_id=10094580&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdudouce%2Fcabinet%2F586%2Fdu255897_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)


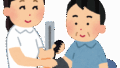

コメント